
「不登校数は過去最高を更新。学校に行けない子のための教育環境の整備が必要では?」
10/27、文部科学省は「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸問題に関する調査結果」を公表しました。
令和2年の段階でも過去最高数を記録していた不登校の子供の数は、令和3年度でさらに増えました。増加率は24.9%と一気に1.25倍になっています。
もはや学校に通えない子供が一定数いる前提で、社会を整備しないといけないレベルだと思います。
今回のテーマは「増える不登校と教育環境のあり方」を取り上げてみたいと思います。
◆不登校数は過去最多のおよそ24万5千人
⇒不登校の割合は2.57%で過去最高
⇒前年からの増加率は24.9%で9年連続増加
◆クラス指導・対面指導の限界が近い
⇒少人数グループ指導が学校にも求められる
⇒学校以外の教育の場が必要。自宅に居ながら必要な教育を提供できる環境整備を!
学習指導だけでなく生活指導と合わせた全体設計が必要
最新の不登校数の調査
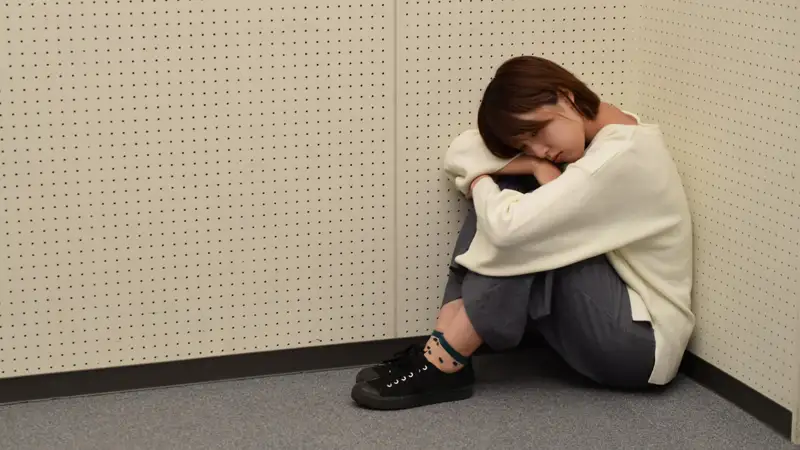
文部科学省は、10/27、2022年度の長期欠席者数の調査結果を公表しました。
小中学校の児童生徒では過去最多の244,940名の子どもたちが不登校である実態が報告されています。
詳細数値は以下の通りです。
| 年度 | 在籍者数 | 不登校による 長期欠席者数 | 不登校による 長期欠席者率 | 増減率 | 新型コロナウイルス 感染回避による欠席 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012年度 | 10,333,629 | 112,889 | 1.09% | -4.1% | ー |
| 2013年度 | 10,299,375 | 119,617 | 1.17% | 6.1% | ー |
| 2014年度 | 10,120,736 | 122,897 | 1.21% | 2.7% | ー |
| 2015年度 | 10,024,943 | 125,991 | 1.26% | 2.5% | ー |
| 2016年度 | 9,918,796 | 133,683 | 1.35% | 6.1% | ー |
| 2017年度 | 9,820,851 | 144,031 | 1.47% | 7.7% | ー |
| 2018年度 | 9,730,373 | 164,528 | 1.69% | 14.2% | ー |
| 2019年度 | 9,643,935 | 181,272 | 1.88% | 10.2% | ー |
| 2020年度 | 9,578,674 | 196,127 | 2.05% | 8.2% | 20,905 |
| 2021年度 | 9,529,152 | 244,940 | 2.57% | 24.9% | 59,316 |
2021年度の小中学生の在籍生徒数は5万名ほど減っていますが、不登校の人数は5万名ほど増えており、過去最多の在籍者の2%を超える状態となっています。
2020~2021年はコロナの影響も考えられますが、コロナによる長期欠席者は別枠が2020年から用意され、そこに6万人ほどの記載がありますから多少の影響はあったにせよ、純粋に不登校の子供はどんどん増えているととらえるべきだと思います。

大人社会でもストレスによる適応障害や抑うつ状態での求職者が増えているわけですから、子どもの世界もどんどんストレスフルになっていると捉えるのが自然だと思います。
子供の居場所たる学校は、教員が忙しすぎて余裕がないわけで、そんな状態で不登校の子供をきちんと面倒を見られるはずがありません。
この状況に対して、どう対処するのかを真剣に考える時期に来ていると思います。
不登校の子供の居場所はどこであるべきか?
11/2、末松文部科学大臣は定例の記者会見で上記の不登校問題への対応について、以下のような趣旨のことを述べています。
- 不登校児童生徒の増加には様々な要因が考えられるため、更なる分析が必要である。今後不登校に関する調査・協力者の会議において分析を行う。
- 不登校特例校の設置促進やICT等を活用した学習活動の充実など、必要な対策を講じていく。

コロナ禍で家庭環境が大きなダメージを受けたことや保護者の意識の多様化が不登校を増やしたという背景もあるようです。とはいえ、10年前の2.5倍規模で不登校が増えていることを考えると、もはや学校のみで対策を講じようとすること自体が限界なのだと考えるべきです。
民間教育を使った不登校児童生徒支援
先生との相性や友達との人間関係、家庭環境、様々な理由で不登校の児童生徒が増えています。
文部科学省は学校にスクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーを置いたり、ICTによる在宅による授業参加などを対策として掲げていますが、それだけで将来社会的に自立した大人になる基礎を子供たちに身につけさせられるのか、なかなか難しいのではないかと思います。
民間教育を使った児童生徒の支援をより強化する必要があると思います。
1.フリースクールの充実
何らかの理由で学校に行くことができない子供たちが、小学校・中学校・高校の代わりに過ごす場所としてフリースクールがあります。
個人経営のものやNPO法人等が運営していることが多いです。日本フリースクール協会という団体が全国のフリースクールの連携強化を進めています。

学校の価値観に合わない子供たちが、自分の個性を伸ばす場所としてフリースクールの充実が急務だと思います。教育委員会・公立学校との連携強化を行い、学校以外の場所での生活で中学校卒業までの資格を与えられるようにすることが大事だと思います。
2.学習塾の機能強化
通常は夕方以降に生徒を預かっている学習塾のうち、フリースクールなどと連携をして、昼間の時間に学習を教えられる塾を増やすことが必要だと思います。
学習塾の中には、少子化で夕方以降のクラスの生徒確保が難しいケースもあり、昼間の開いている時間を指導に充てることで塾側の経営安定化も図れる可能性があります。
また、不登校の生徒の中には、勉強を頑張りたいという子供も一定数いるので、その子供たちに必要な学びの機会を確保することは、園子自身の将来にも重要な意味を持っていると思います。

すでに一部の学習塾では、フリースクールと連携して不登校支援を行っています。増える不登校の児童生徒にも様々な才能が隠れていますので、それをつぶさないように大人の責任として子供たちを引き上げる環境整備をすべきです。
不登校児童の今後の動向と学習塾やフリースクールによる支援体制強化に注目していきたいと思います。
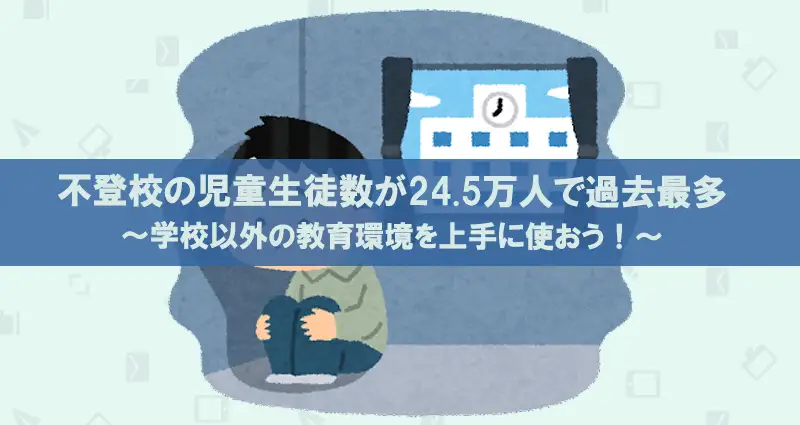
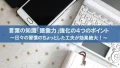

コメント