
こんにちは。まさおです。
首都圏の中学入試日程はほぼ終了を迎え、これから高校入試が本格的にスタートします。コロナ急拡大で当日受験が不幸にしてできなかった場合の救済策として、追試験の設定が広がっていますが、公立高校の中でも「推薦」「前期」を中心に追試験のない試験がいくつか存在しています。どう対処すべきでしょうか。
今回のテーマは「追試験のない公立高校対応」です。
◆推薦入試・前期選抜に追試設定なしが多い
⇒自治体の説明は「後期選抜」「一般選抜」に回ってほしいとのこと
⇒選抜方法が全く異なる後期選抜等では合格可能性が低くなる
◆受検生はコロナ罹患時の対応をあらかじめ想定して準備
⇒基本は感染回避で当日受験できる状況を確保すべく努めること
⇒万が一の場合は中学の先生・高校側への強い申し入れをした上で後期を受検する
万が一の際にはきちんと制度の不備を指摘することが重要
主要自治体の追試験対応状況
1月になってから新型コロナウイルスが急拡大し始め、今年の入試は大混乱の中で進んでいます。
12月当初は感染が少なかったため、昨年の入試よりも落ち着いた入試になると思っていたところも多く、対応が後手に回ってしまった感も否めません。
文部科学省は「受験機会の最大確保を」という方針で、追検査の設定を促していますが、「推薦選抜」「前期選抜」を中心に追試験の設定がないところも多く、注意が必要です。
リセマムが状況まとめた記事を掲載してくれていますのでご紹介します。
◆主要都道府県の対応が見られるページは以下から
◆各自治体のコロナ対応ガイドラインリンク集は以下から
たとえば、上記記事のうち、群馬県の事例を取り上げてみます。
追検査は、全日制課程・フレックススクール後期選抜または定時制課程選抜に志願した者のうち、新型コロナウイルス感染症感染者または感染が疑われる者、学校保健安全法第19条で出席停止の扱いが定められている感染症に感染し選抜当日受検できない者、および本人の責に帰さない理由により受検できない者で当該選抜のすべてを受検できない状況となり、当該高等学校・学科等における追検査の受検を希望する者を対象に実施する。
<追検査>2022年3月24日(木)
リセマム記事より。下線はまさおが追記。
上記の通り、後期選抜を志願したもののみが対象となっている状況が起こっています。

多くの自治体が「学力検査を欠席した場合に追検査を実施する」としている通り、学力検査や作文に対する追検査設定は多いものの、面接や推薦入試の追検査の設定はあまり想定されていないようです。
埼玉や神奈川、千葉のように後期選抜のみしかない自治体はよいのですが、前期選抜が存在するのに、追検査は後期のみに設定というのが問題です。
前期選抜・推薦選抜で追試なしのケース
前期選抜・推薦選抜に追検査が設定されていないことは、制度上はかなり不公平感があります。
前期選抜・推薦選抜の多くは、生徒の個性を重視する特色のある選抜を行っているケースが多く、部活動の大会での実績やコンクール等での実績をベースに判定されます。
一般入試と異なり学力検査以外が重視されるため、その受験生が追検査に回ったとしても実力が発揮できるとは限りません。
上毛新聞ではこの問題を取り上げて以下のような記事が掲載されています。
推薦入試の多くは面接試験と調査書で大半が決まるケースが多いため、追検査の設定は不可能ではないはずです。
仮に特色検査問題が特殊で設定ができなかったとしても、私立高校ならまだしも、県公立高校であるなら住民への公平な対応が必要で、特例検査として受検機会を面接のみでも確保するべきではないかと思います。
受検生はどう対応すべきか
受検生はこの問題にどう対応すべきでしょうか?
ポイントをまとめました。
- 感染回避を徹底し予定通りの受験を目指す
⇒学校を休むことや家族と別の部屋で生活するなど感染リスクを低減させる行動を徹底して当日受検をできるだけ目指す - 受検できなかった時の追検査対応を改めて確認
⇒万が一の感染や濃厚接触者となって受検ができなかった場合どのような対応をするのかを改めて確認しておく - 万が一受検できなかった場合は、中学・高校双方に申し入れをする
⇒万が一受検ができず、追検査が難しいといった場合は、中学の先生と高校側の双方に対応の不備を申し入れておくこと - 申入れ後に指定された方法で受検する
⇒合格発表で合格すれば終了。 - 不合格時に再度特例追試を申し入れる
⇒万が一不合格時にはもう一度申し入れを行い特例追検査ができないか確認
上記の通り、問題なく受験できればベストですが、それ以外でも何回か相談や申入れをすることで合格を引き寄せる可能性があると思います。
自治体・高校側も公務員なので四角四面な回答をしてくる可能性がありますが、本当に推薦入試で合格させたいほどの実力があれば、何らかの対応を検討してもらえる可能性はゼロではありません。
重要なことはあきらめずにできうる手段をとるということです。

公立高校は全体の倍率としては突出して高い学校は比較的少ないので、まずはきちんと受験をして合格を目指す道筋を追求することが重要です。
その上で、コロナ禍の特殊事情について適切な考慮や対応を求めていくことも、必要に応じて進めていくとよいでしょう。
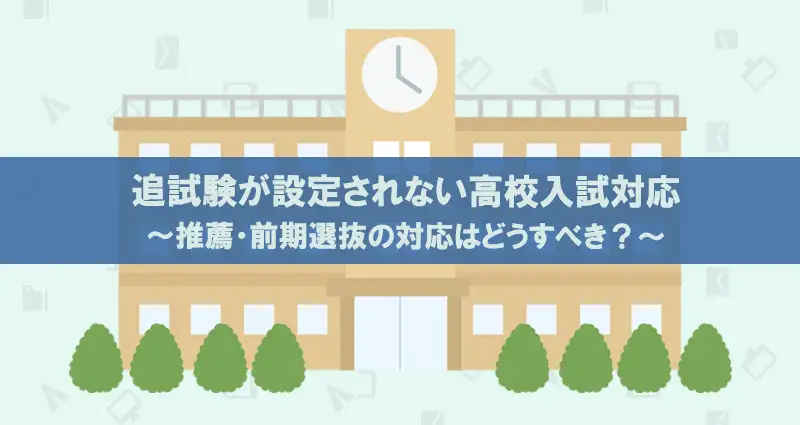
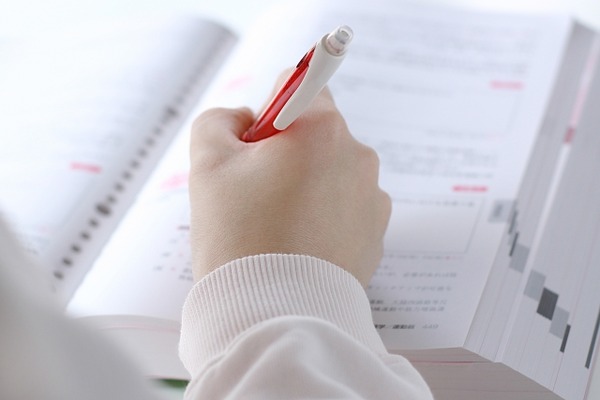




コメント