
これまで断片的に書いてきた記事もなんだかんだで100本ほどになりました。
そろそろ体系化してまとめようと思います。
今回は国語の読解力アップの方法です。
1.文章に向き合う心構えを作る
2.言葉の知識を増やす仕組みづくり
3.出題形式別の解答の導き方の理解
4.記述式解答の書き方作法
この4つがきちんとできていれば、かなりいけるはずです。
読解の基本となる心構え
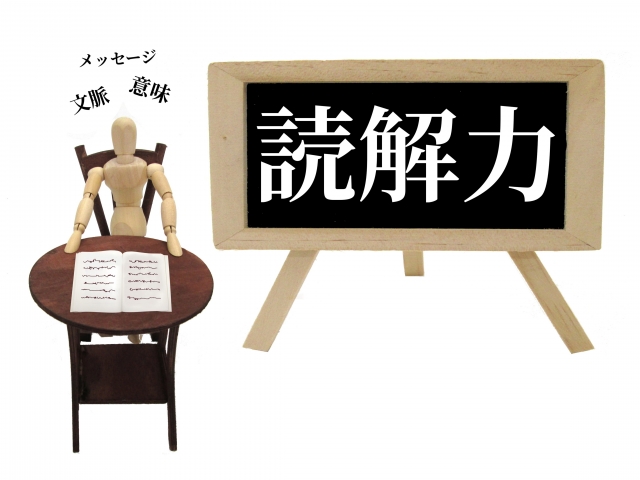
読解問題を解く際に重要なことは、向き合う姿勢です。
最初から苦手意識全開で、腰の引けた態度で文章に接していても絶対に結果は出ません。
目の前の文章に真正面から向き合って、内容をつかみ取ってやるという気概と、冷静に文章の前後関係を読み取る目が備わっていれば、勉強などしなくても成績は上がってきます。
言葉の知識を増やす仕組みづくり
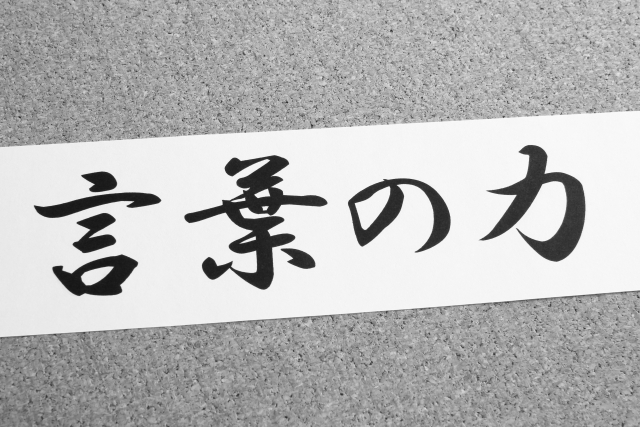
心構えができたら、次に必要なことは知っている言葉の数を増やすことです。
語彙力はなんとなく待っていても増えません。自分ので知らない言葉を知ろうと努力する姿勢が必要です。
まずは漢字練習を定期的に進めること、次に知らない言葉にマークをつけること、この2つができるだけで、目に見えて言葉の知識は増えていくはずです。
出題形式別の解答の導き方の理解
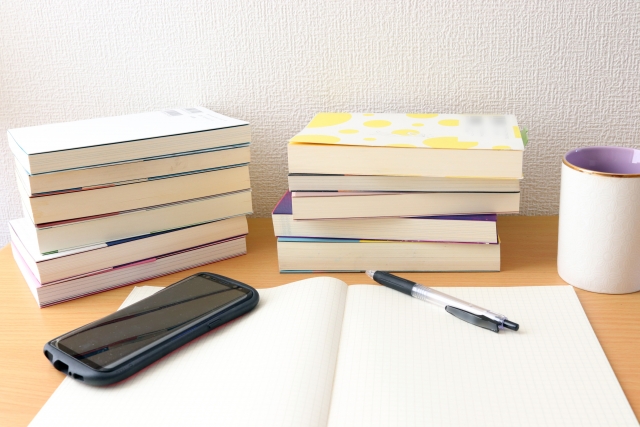
姿勢ができて、言葉の知識がある程度身に付いたら、国語の成績はもう上がり始めているはずです。
それにさらに輪をかけるのは、出題形式別の解答の仕方の理解です。
選択式問題の解答作法
選択式問題は、出題者側が回答の主導権を握っています。出題者が受験者に乗っかってほしいと思っている内容をくみ取れれば正解にたどり着けます。
具体てな手順として以下を意識しておきましょう。
①設問文を読む
②下線部の内容確認
③下線部の前後の文の確認
④選択肢の確認
上記の手順を飛ばさずに、1文字1文字漏らさず読み取る姿勢ができれば、正解率は絶対にあがってきます。
空欄補充問題の解答作法
選択式問題に対応するすべを身につけたら、次は空欄補充です。
空欄補充には知識系と読解系がありますが、今回は読解系の空欄補充に注目をしましょう。
読解系の空欄補充は、①前後関係を丁寧にたどることで回答にたどり着けるタイプ、②空欄前後の表現と同じことを述べている別の個所から解答を引っ張ってくるタイプの2種類があります。
以下の記事で詳細を説明していますから、一度丁寧に読んでみてください。
記述式解答の書き方作法

最後に確認すべきは記述氏の解答形式への対応方法です。
字数制限によって、多少対応手順が変わってきます。
30~100字程度の記述問題への対応方法
①設問内容を正しく理解する
②下線部やその前後から必要な情報を得る
③解答の中心内容をぼんやりとした言葉で決める
④解答の中心内容に字数制限などの条件に合うよう文字を足して、解答を整える。
多少の練習が必要ですが、上記プロセスをきちんとたどれるようになれば、問題数をこなしていくうちに正解率が上がってくるはずです。
200字程度の作文の書き方
100字程度の記述まで書けるようになっていれば、通常の筆記試験はほぼ問題ないはずです。
一方で200字程度の短い作文は都県率高校入試などではよく出題されます。
これについては、ある程度型さえ作ってしまえば、あとは少しの練習で十分ものになると思います。以下の記事で確認をしておきましょう。
600~1200字の入試小論文の書き方
さらに字数が増えて600字を超えてくると、制限時間も長くなり、解答作法も変わってきます。
小論文は作文とは違った作法が求められますので、以下の記事内容をきちんと読んで正しい練習を積んでいく必要があります。

作文・小論文は入試が近づいてからの対応でも間に合いますが、読解の心構えから空欄補充あたりは1学期からきちんと得点できるように丁寧に記事内容を読んで身につけておきましょう!


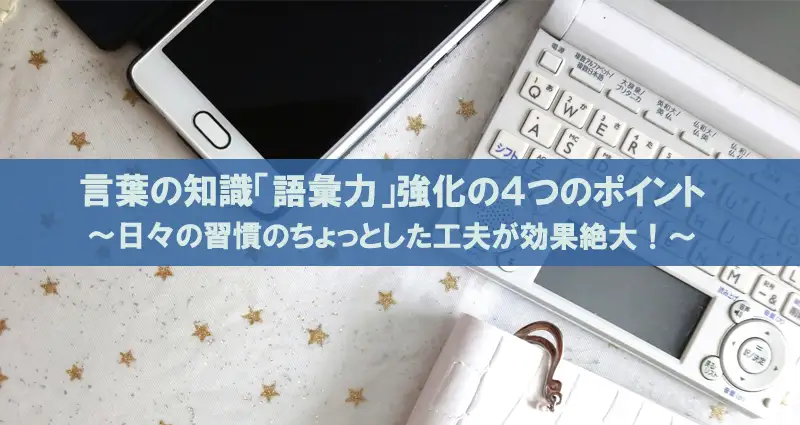




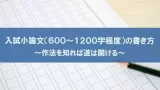

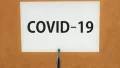
コメント