
こんにちは。まさおです。
12/11のNHKのニュースで産業能率代の入試が取り上げられていました。スマホを使って調べる入試を導入するということです。
今回は「今後の入試問題はどうあるべきか?」というテーマを取り上げます。
◆知識を問う問題は順次減少していく
⇒知っている知識を答えるタイプの問題は今後減少していく可能性が高い
⇒調査やレポート型の入試は採点が大変なので、受験生が多い大学は導入しづらい
◆厳密な採点を求める入試問題から緩やかな評価へ移行していく
⇒入学時のハードルを高めるのではなく卒業を厳しくする方向へいくはず。
産業能率大の入試問題とは?
産業能率代が2021年2月に実施する入試について、NHKが報じていました。
・スマホやタブレットで情報を調べてもよい入試
・与えられたテーマに対して解決策を記述式で答える
・集めた情報を応用する思考力をみる
・共通テストで一定の得点を取るなど受験のための基準がある
・試験問題の外部総進などの不正防止の対策も行う

大学側も手探りでの実施だと思いますが、知識ではなく情報活用能力を見る入試は今風だと思います。採点が大変なので、問題の作り方に工夫がいると思います。
これからの入試は記述式が増えていくはず
知識偏重から、思考力・判断力・表現力重視の入試へ移行していくのは間違いないのですが、思考力・判断力・表現力をある程度見極めるためには、一定字数の記述問題を課す必要があると思います。今の大学入試は公平性や正確性を厳密に求めるため、大胆な記述問題などを出しづらい状況があります。
一方で、入試の公平性や正確性をどんなに担保しようとしても、これからの時代はそのような入試を実現すること自体が難しくなっていきます。
毎年多数の大学が入試問題の不備を公表し、追加合格者を出しています。
入試問題と言えども人が作る問題である以上、不備や欠陥はゼロになりません。
むしろ、これからの時代はそのような不備や欠陥がある前提で入試性を考えていく必要があるように思います。
出願期間中に与えられたテーマのレポートを提出してもらい、入試本番は面接試験でそのレポートの内容について質問をするといったやり方がこれからの時代の入試になると思います。そのレポート内容が本物かどうかを面接で様々な質問により明らかにするというのが、これからの入試の主流になっていくでしょう。
大学入学者を選抜する入試よりも卒業を厳しくする方が現代的
このような状況を総合的に見ると、今後20年くらいの間に大学入試の正確性というのがだんだんと失われていくのではないかと思います。
むしろ、入学時は本人に通学の意志があるなら、多少緩くても合格させてしまい、その後本当に大学に積極的に通って自分の力を磨いていくかを見ていく方が良いと思います。
これからの時代は、大量の情報を正確に扱うことが難しくなる時代で、入試のように多くの受験生答案を公平に正確に扱うこと自体も大変な労力を割く必要が出て来ます。
一方で、マークシート入試のような大量かつ一括処理をするものがだんだんと肩身の狭い状況になるわけですから、もともと公平性など担保されているはずもない面接試験のようなものに、ある程度の労力をかけてシフトしていかざるを得ないということになります。
その際に、1点で人生が大きく変わってしまうというような分岐点をある瞬間で作るのは得策ではなく、何回かのチャンスの積み上げで総体的な評価をしていく方向に動くと思います。

大学入学共通テストも色々思考策をしていますが、当面マークシートからは脱却できないでしょう。記述問題の採点は50万人を超える大量処理を正確に行うのはまず不可能で、正確性を放棄するか大量処理を辞めるかの2択が迫られるはずです。
そうなると、国公立2次や私大の個別試験のあり方の方が問われることになります。2年近くかけて問題を作っても1つのミスで袋叩きに遭う今の制度はそろそろ限界と考えるのが正しいものの見方だと思います。
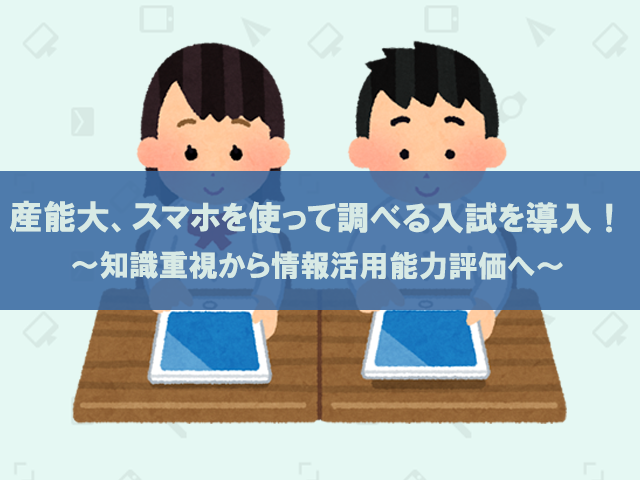
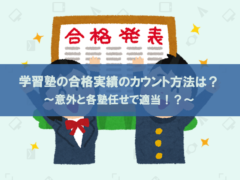
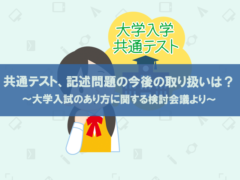
コメント